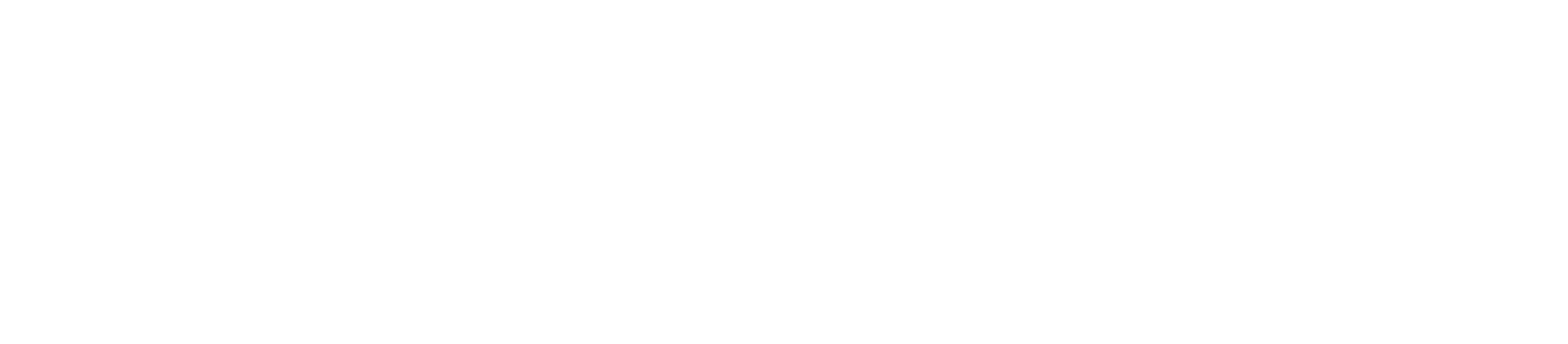塩冶掃部介の墓の感想
あまり知られていない戦国武将だとは思われますが、私にとっては非常に興味深いキーマンとなる武将です。私が読んだ小説では若き頃の尼子経久と塩冶掃部介は切磋琢磨した間柄であり、応仁の乱など早くから京に在京し西軍の中心になっていた武将です。尼子経久とは旧知の中でよきライバルでもあったと想像していました。
塩冶氏は出雲国の有力な国人衆で出雲国の守護職京極氏の家臣でもありました。
塩冶掃部介は通称は荒法師と呼ばれていたことから、武力に優れた武将だったんだと思われます。尼子経久が京から戻り出雲国で徐々に勢力を拡大し主君の京極氏をも超えるものとなり始めると、阿用城の桜井宗的などと同じ旧来の武家社会を重んじる塩冶掃部介は、守護職の京極氏が出雲国を治める秩序を望んでいたのかもしれません。
出雲国守護職京極氏が守護代の尼子経久の振る舞いに怒り、出雲国の国人衆も集め月山富田城を攻撃し尼子経久を追放してしまいます。 その後、尼子経久の代わりに月山富田城に入城し守護代になったのが塩冶掃部介でした。
浪人になった尼子経久は奥出雲に身を隠し月山富田城の奪還を狙い続けます・・・奥出雲の蜂屋衆(鉢屋衆(はちやしゅう)は祭礼や正月に芸を演ずる芸能集団であり兵役も務めた。鉢屋党とも呼ばれています。人里から離れ特殊技能を有しており全国に飛び散っており、筑波山や箱根山などで特殊技能をもった武力集団として存在しています。奥出雲の蜂屋衆は製鉄技術に長けており強靭な体と弓矢の技術に優れていたとされています)を味方につけ、1486年の元旦に毎年恒例の万歳が行われます。月山富田城では祝いの舞を演じることになっていた。午前3時ごろ賀麻党七十余人は笛や太鼓でにぎやかに城内に招き入れられ、尼子経久はその蜂屋衆に紛れ烏帽子の中に中に兜をかむり、素襖の下に具足をつけ武器を隠し持って武装していたと云われています。その時にかねてより忍び込んでいた経久の一党は太鼓の合図に経ち城内各所で火を放ち乱入!!!それにあわせ賀麻党も烏帽子を捨て手薄だった城内で襲い掛かります。城主の塩冶掃部介は尼子経久の奇襲に支えきれないと判断し自害したと云われています。
塩冶掃部介と尼子経久との関係は深かったんじゃないかと個人的には思っています。今は寂し気な場所に塩冶掃部介の墓がありましたが、新宮党館跡と月山富田城の間の麓にありました。
塩冶掃部介の墓画像ギャラリー




塩冶掃部介の墓情報
| 年 代 | 1486年没 |
| 住 所 | 島根県安来市広瀬町富田 |
| 種 別 | 史跡 |
| 入場料 | 無料 |
| 営業時間 | – |
| 駐車場 | 無し(月山富田城駐車場など利用) |
塩冶掃部介の墓へのアクセス
塩冶掃部介の墓レビュー
塩冶掃部介の墓についての皆さんの評価をお願いします。
塩冶掃部介の墓おすすめの理由や訪問時の感想などもご記入いただけると嬉しいです。